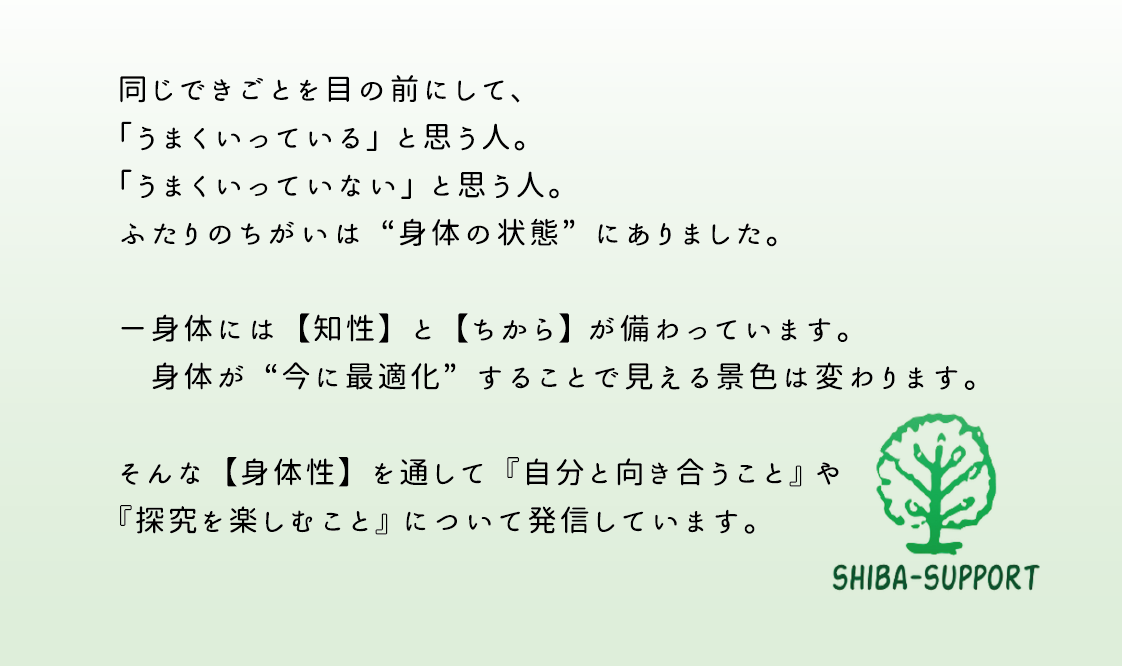-Contents-
2・3代目信者さんの罪悪感と責任感
こちらの記事で、
依存的な信者さんについてのお話に
触れました。
いわゆる
「宗教の勧誘をしてくる人」
の典型的なイメージですよね。
しかし、
このブログを読んでくださっている方のなかには、周りにそういった依存的な在り方で信仰をしている人はそれほどいない、という方が多いかもしれません。
一番身近なところでいうと、
お祖父さんやお祖母さん、
ご両親や兄弟などの家族。
もしも、
家族の在り方がとても依存的で
宗教のために生活や経済状況にまで
影響がでている・・ということなら、
きっと悩みませんよね。
悩み方がちがうと思います。
それほど恩恵も感じられず、
あきれ果て、
一線をひくことにエネルギーを
注ぐかもしれません。
宗教という批判の対象があることは、
むしろ原動力にすらなるかもしれません。
意外と多い宗教2・3世の悩みは、
『信仰の価値を知っているからこそ、
自分の人生を生きることに罪悪感がある』
というものです。
私の場合もこのパターンでした。
信仰があることで
家庭が破綻するようなこともなく、
むしろ安穏な環境で過ごさせてもらってきた
と思います。
両親も穏やかな、
とても中庸な考え方ができる人たちで
朝が早いので若々しいです(笑)
だからこそ、
「宗教のための生き方」から
「自分のための生き方」に
変わろうとするときは大きな《罪悪感》
に襲われました。
宗教的な価値観をベースに
そこには安穏な日々がある、
その恩恵もあって幸せ感度も高かった。
私だってそうやって生き続けていけば
このまま穏やかに過ごしていけるのに、
どうしてか違和感を感じてしまう。
ちょっと生き方を変えてみたい
と思ってしまう。
変えなければと思ってしまう。
やっぱり自分はなにか
至らないのだろうか?
未熟なんだろうか?
大切なことが見えていないのだろうか?
いっそのこと、
目の前にある状況が
めちゃくちゃで破綻していたほうが
あっさりと方向転換できたはずです。
宗教を否定するときの
典型的な言葉に、
『そんなお祈りだけして思い通りに
いったら人生苦労しないよ』
というものがあります。
しかしながら、
実際に信仰のある環境に
身を置いているなかで、
そういうタイプの人は実は少ない
という事実を見てきました。
そうしたタイプの人は、
最初の奇跡的体験を大きく取り上げて
舞い上がりはするけれど、
長くは続かないからです。
むしろ、
何代かにわたってその信仰を
続けている、という人の場合、
“自分がなんとか頑張らなければ、
役目を果たさなければ・・・”
と自分を鼓舞し、ときには自分を責めて
自立しようとする傾向が強かったりします。
そしてその原因は、
宗教の教えそのものではなく、
その人自身のこれまでの成育歴や
処世術に起因していることも多いです。
成育歴とは育ってきた環境や
その歴史のことですね。
男性によくあるケースで、
こんなものがあります。
お母さんがとても信仰に熱心な人で、
その方が信仰に前向きな姿勢を示すと
とても喜んでくれた。
男の子にとって、
お母さんの笑顔や喜びって
本当に格別なものですよね。
幼い男の子のなかにある、
“お母さんにもっと褒めて欲しい”
“お母さんにもっと認めて欲しい”
“お母さんにもっと喜んで欲しい”
という気持ちは、大人になった男性の奥深くにも潜んでいます。
男性にもその自覚はないし、
ただ信仰に対して熱心なだけにも見えるのですが、実はそんな幼心が彼を信仰熱心にさせている、ということもあります。
実はそこに宗教的な問題、
というのはあまりなく、
根底にあるのは“親子間の依存”です。
お母さんは、
とても一生懸命に“母親”という役割を
果たしてきました。
自分の時間もお金も犠牲にして
一生懸命に子供を育ててきました。
母性本能というものももちろんあるし、
世間もそれを求めてくるので当然のこと
ですよね。
しかし、
そうした一生懸命さの積み重ねが、
【子供の在りよう=自分への評価】
という無意識の方程式を生んでいきます。
子どもが成績優秀だと(自分が)〇、
そうでないと(自分が)×、
子どもが皆勤賞だと(自分が)〇、
引きこもりだと(自分が)×、
子どもが信仰に熱心だと(自分が)〇、
そうでないと(自分が)×。
宗教的なことに関わらず、
この方程式は、
お母さん自身が自分の価値を認めず、
【母親】という役目に依存していることで
生まれるものです。
特に、
宗教的な環境というのは、
身のうえ話をすることが多いので
意外にも【人と比べてしまう】
という機会が多いんですね。
“うちの子がうまくいかないのは
私のやり方が悪かったのかしら…”
なんて自分を責めてしまうことだって
起こりがちなことです。
そして、
子どもというものは、
お母さんのことをよく見ているので、
自分がどうすることをお母さんが望んでいるのかを深いところで察していきます。
お母さんが喜ぶであろうことに
一生懸命になります。
そうして成長して大人になったとき、
“あれ?なんかちがう?”
そんな戸惑いが湧いてくることがあります。
それに罪悪感が伴うこともあります。
お母さんと男の子にあった
親子間の依存もそうですが、
その原因は
“お互いが外側に自己の価値を置いている”
ことにあります。
“親として”
“子として”
役割を果たさなければならない、
という責任感。
それが果たせないかもしれない、
という罪悪感。
その根底には、
“自分には価値がない”
という思い込みがあるかもしれません。
そして
確実にいえることは、
その人自身の性分が
“真面目で優しい”ということです。
真面目さゆえ、
優しさゆえ、
生きづらさを抱えるのは
なんだか損ですよね。
無価値観を乗り越えることも
持ち前の責任感の強さを
気持ちよく生かしていくことも、
“自分と向きあうこと”で解決できます^^
“自分と向き合う”って修行?
宗教的な価値観を大切にしてきた人や
自立志向が強い人ほど、
“自分と向き合う”という言葉に、
「これもまた修行なんですね」
という反応をしてしまうことがあります。
なにか問題が起きたり、
転機がおとずれたりしたときは
努力をしたり、責任を果たすことで
それを乗り越えたり、成長の糧にしてきた。
そんなこれまでの思考や行動のくせで、
“自分と向き合う”ことに対しても、
気合をいれて重い腰をあげようとします。
重い腰をあげなくたっていいんです。
むしろ立ち上がらないでください。(笑)
“腰が重いな”
と感じながら、そのまま座っていること。
それが
“自分と向き合う”ということであり、
“自分を知る”ということです。
努力をしたり、積極的に動かなくても、
「自分を知ってみよう」という意識をもつだけで自分のなかから湧いてくるものです。
今は“でてきていいよ”という許可が自分で
だせていないだけなんです^^
前回の記事でお話した、
“自分と向き合う”ということについて、
そのやり方が想像よりも生温くて
ビックリされたかもしれません(笑)
自分の感じていることに対して、
赤ちゃんをあやす感覚で…
なんてこれまでの生き方からしたら
拍子抜けですよね^^
でもこれ、
よく考えてみると、
そんなに甘いだけの理屈では
ありません。
突き詰めていくと、
“神仏や他人に自分のおしめを変えさせない”
ということなんです。
なんだか矛盾しているような
感じがしますよね^^;
私はこのことに気づいたとき、
“あぁ自分を大切にするって
そういうことか・・!!”
と愕然としました。
それまで、
自分を優先したり、
自分を労わったりすることに、
なんとなく甘えのようなものを
感じていました。
でも、
その裏では、
甘えることを許さず、
正しさに忠実であることで
なにかを与えてもらえることを
どこかで期待していました。
自立的でいるようで、
実は依存的だったんですね(^-^;
言葉や意識のうえでは、
なんとなく感謝って大切・・
みたいに思っていたのに、
いつも私を支えてくれてる思考や
思考と同時に動いてくれる身体を
労わったり意識してあげることが
できていませんでした。
なんということか、
自分のケアが他人まかせだったんです。
つまり、
自分を優先したり、
自分を労わったりすることは、
真の自立への第一歩になります。
これまで求められたのは、
鋼のようなピーンとした強さ
だったかもしれません。
でも、
こちらの記事でお話したように、
これから求められるのは、
柳のようなグワンとしたしなやかさ
です。
どっちにもいけるよ~、
私はこっちを選ぶよ~、
という柔軟かつ意志のある姿勢が
自然体で楽に生きるための秘訣
なのかもしれませんね^^
“良いとこどり”ができない
「宗教中心の生き方」から
「自分中心の生き方」へ
変えていこうとするとき、
“良いとこどり”をしているような
嫌な気分を感じることがあります。
この嫌な気分の正体が
『罪悪感』です。
“良いとこどり”を柔軟性と捉えたら、
少し楽になりませんか^^
“良いとこどり”って決して調子乗り
なわけではありません。
“良いとこどり”には選択がつきまといます。
そして選択には責任がつきまといます。
はいってくる言葉や情報を選択しなければ、
“良いとこどり”はできません。
前述したように、
このブログを読んでくださっている方には、
『責任感』という強みが既にあります。
その『責任感』の使い方を
変えていくだけでOKなんです^^
鋼のような強い自分であろうとすると、
自分らしくいられなくなります。
「信者として」
「3代目として」
「長男として」
「上司・先輩として」
のように自分でも気づかないうちに
何者かになろうとしてしまうんですね。
そして気づけば
“選択すること”や
“自分で決めること”に恐れがでてくるようになります。
しかし、
柳のようなしなやかな状態であろうとすると、
自然に自分らしさがでてきます。
何者かとしてではなく、
「自分として」
どうなんだ、という視点をもつと、
根底にある『責任感』を
“選択する”、“決断する”
ということに発揮していけるようになります。
私は、
信仰上の教えのうち、
“自分を非力化してしまいそうになる考え”
は採用しないと決めています。
最初の頃は、
《罪悪感》が湧いてきて
しんどいなぁと思うこともありました。
お腹のあたりがきゅうっとして、
背中もこわばって
呼吸も浅い状態でした。
けれど、だんだんと
「私で決めていい」という許可を
自分でだせるようになってくると、
《罪悪感》も消えていきました。
お腹もゆったり、
背中から力もぬけて
呼吸も深くなってきました。
《罪悪感》のもうひとつの正体は、
自分の考えで判断したら
辛いめに遭うかもしれない、
損をするかもしれない、
という“恐れ”という名の、
保証や安定にしがみつく心でした。
そして
誤解がないようにお伝えしたいのは、
『自分らしく』なることが最上ではない、
ということです。
自分と向き合ってみた結果、
『何者』かとして生きる方が楽だ、
とご自身が決めた場合、それは大正解です!
なので気楽に、
身体と心の力をぬいてみてくださいね^^
——–
Q.「ソマティック(身体性)とは?」
●【概念編】
⇒思考(左脳)と身体感覚(右脳)のちがい①~⑤・<最終章>
※<最終章>までの連続シリーズです。
●【本質編】
⇒ソマティック(身体性)な探究~本質編~
●このブログでは、
【パーツ心理学】にもとづいて、
身体の細胞や感情に対して
“擬人的”な表現を多く用いています。
自分と向き合ったり、
感情と距離をおくことを優しく
手伝ってくれる神経生物学的な考え方です^^